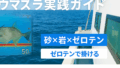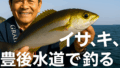真鯛は、見た目の美しさと引きの強さから「釣り人の憧れ」と呼ばれる魚です。
瀬戸内では水深や潮の変化が豊富で、季節ごとに狙い方が変わります。
この記事では、元船長の経験をもとに昼の瀬戸内で真鯛を釣るためのコツをわかりやすく紹介。
潮が当たる場所の選び方、仕掛け、誘い方まで、初心者でも再現できる実践ポイントをまとめました。
初心者の方は用語が不安なら、先に 「真鯛、用語ミニ解説」 をご確認ください。
真鯛、釣れる時期とポイント選び
真鯛のハイシーズンは春(4〜6月)と秋(9〜11月)。春は産卵前後の大型狙い、秋は数釣りが中心になります。潮通しの良い場所、特に瀬や岩礁が絡む「潮目の変化点」に真鯛は付きやすく、瀬戸内では水深40〜60m前後のブレイクラインが鉄板ポイントです。
姫島沖の真鯛釣り、実際の状況とポイントの特徴
大分県・姫島沖は瀬戸内でも潮の動きが速く、潮止まりと流れ始めの変化がはっきりしているエリアです。春先と秋に群れが寄りやすく、朝まずめ〜7時頃が特にチャンス。潮が緩むと真鯛が浮き上がり、軽めのテンヤやタイラバ(60〜80g)でゆっくり誘うのが効果的です。
反対に、潮が速い日は100gのヘッドを使い、底を確実に取ることを優先します。着底直後の“コンッ”という小さな違和感を逃さないことが、姫島沖の釣果を分けます。鯛の活性が良い日には、釣り始めるとすぐにヒットし、鯛の独特な三段引きが始まりガン・ガン・ガーンと竿を大きくしならせてくれます。この海域には数多くの漁礁があるので、実績のあったポイントを次々に攻めていきます。
真鯛の釣り方、タックルと仕掛け選び
- ロッド: タイラバ専用またはテンヤ兼用のML〜Mクラス
- リール: 小型両軸リール(カウンター付きが理想)
- ライン: PE0.8〜1.2号、リーダーはフロロ4号
- 仕掛け: タイラバ(60〜120g)またはテンヤ3〜8号
潮流と水深に合わせて重さを変えることが釣果アップのコツ。また、ベイトが小さい時期はネクタイを細くするなどの微調整も有効です。
真鯛の釣り方、誘い方とアタリの見極め
誘いは「一定のスピードで巻き上げる」のが基本。途中で止めたり、早巻きに切り替えたりとリズムをつけて魚の興味を引きます。アタリは“ゴツン”ではなく、“重みが乗る”ような感覚で来ることが多く、そこで慌てず一定スピードを保ちながら、真鯛の食い込みを待つのが鉄則です。
真鯛の釣り方、初心者が注意すべき点
- 底取りを怠るとアタリが出ない
- 潮が速い時は重めに切り替える
- ラインテンションを常に保つ
- 仕掛けの落下中も気を抜かない
真鯛は「潮読み」と「タックル操作」が釣果を左右します。焦らず、一流しごとに状況を整理する意識が大切です。
真鯛の釣り方、まとめ
姫島沖をはじめとした瀬戸内海では、潮流・地形・季節を読み解くことが釣果の決め手になります。経験を重ねるほど、海が語る“サイン”が見えるようになります。次に竿を出す時は、風や潮の匂いにも耳を澄ませてみてください。きっと、真鯛が寄ってくる瞬間がわかるはずです。
真鯛、用語ミニ解説
- 潮目:水面の色や模様が変わるライン。異なる流れがぶつかる境でベイトが寄りやすい。
- ブレイク(ブレイクライン):海底の段差・かけ上がり。潮が当たり、魚が付きやすい境目。
- まずめ:夜明け・日没前後の薄明時間帯。回遊性の強い魚の活性が上がる。
- タイラバ:鉛(またはタングステン)ヘッド+スカート・ネクタイのルアー。一定巻きが基本。
- テンヤ:オモリと針が一体化したエサ釣り仕掛け。底取りが明確で誘いが細かく出せる。
- 三段引き:真鯛特有の「ガン・ガン・ガーン」と段階的に引く強いファイト。
タグ: 真鯛, 瀬戸内, 船釣り, 仕掛け, 季節, 元船長の実戦録, タイラバ