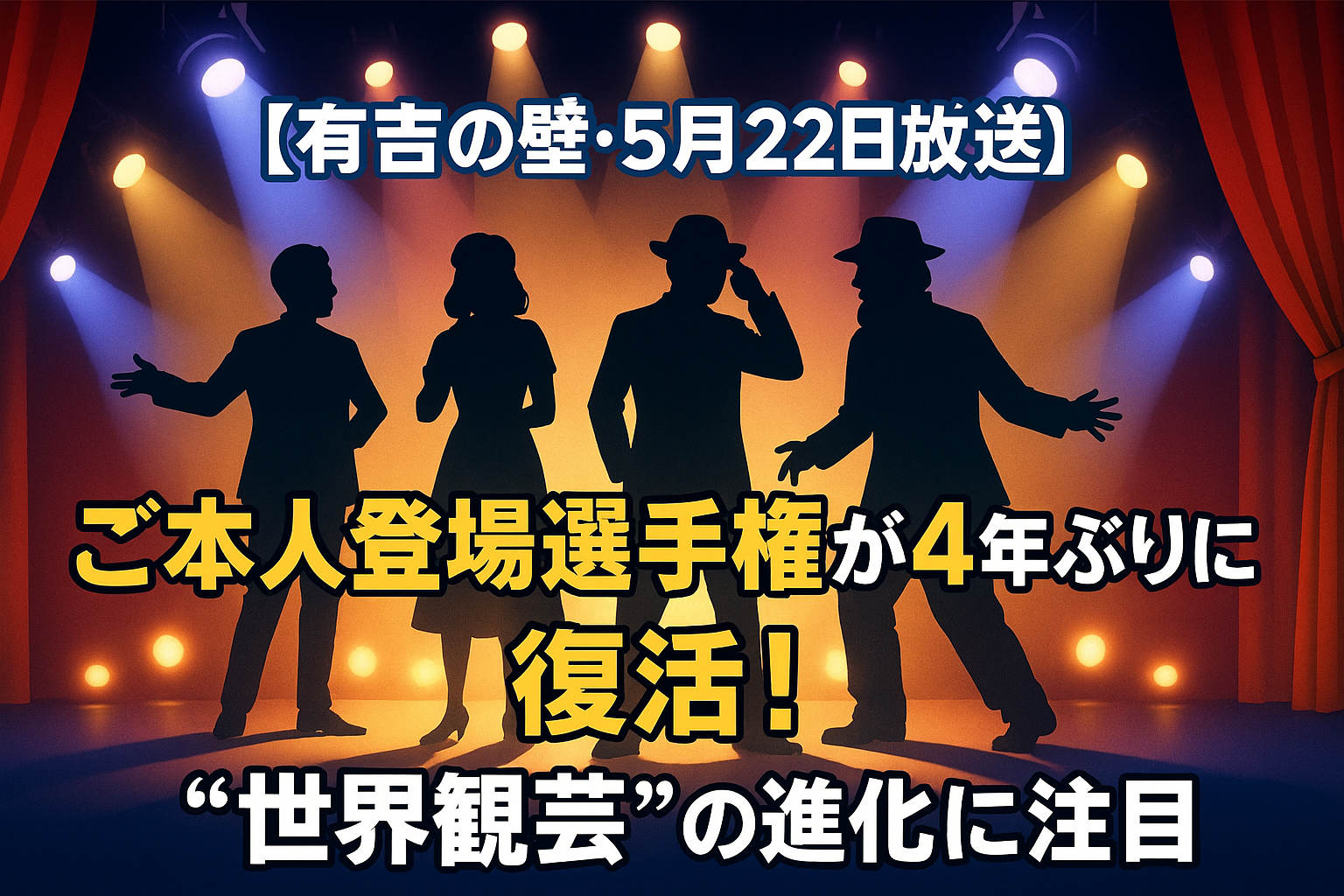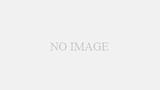####「バカバカしい」だけじゃない、有吉の壁の奥深さ
『有吉の壁』は、芸人が即興で笑いを取るという過酷な番組。
しかし見れば見るほど、そのネタには「一発ネタ」の域を超えた“物語性”があることに気づかされます。
この記事では、有吉の壁がなぜ「世界観芸」の宝庫なのかを、具体的なネタや芸人の技術から読み解きます。
#### 【分析①】“ご本人登場選手権”は世界観勝負
番組名物の「一般人の壁(=ご本人登場選手権)」では、芸人たちが“お店の従業員”などになりきって登場します。
注目すべきは、ただ変な格好をして笑いを取るのではなく、
登場時からセリフ、動き、背景設定まで一貫した“キャラ作り”がされていること。
例:陣内智則さんが「カフェのオーナーで全メニューがウソ」など、設定だけで世界観が笑いになるケースも多数。
これはもはや“即興コントというより短編演劇”に近く、芸人の構成力と演技力が問われるステージです。
—
#### 【分析②】芸人ごとの「世界観ジャンル」が確立されている
『有吉の壁』では、芸人ごとに“持ち味の世界観”が存在します。
– ジャングルポケット → 「ギャグマンガ調」の高速ボケ世界
– シソンヌ → 「静かな狂気」と「中年のリアル感」
– さらば青春の光 → 「昭和あるある」×「クセの強い人物描写」
視聴者は「この人たちは、どんな変な世界を見せてくれるのか?」という期待で見るようになり、
ネタそのものが“一つのジャンル作品”として楽しめる構造ができています。
—
#### 【分析③】“キャラ芸”が即興でも破綻しない設計力
注目すべきは、ネタが即興にも関わらず「破綻しない」構成力。
どんな小道具やセリフが飛び出しても、“キャラとして反応する芸人力”が支えています。
ぺこぱ・ザ・マミィ・空気階段などは、「キャラが生きているから何をしても成立する」構造を持っており、
即興でも“世界観の中で生きている感”が途切れません。
この「設定を守りつつ笑いを生む力」こそが、有吉の壁芸人の強さです。
—
#### 【筆者の感想】「一瞬で物語が始まる芸」にハマった理由
私が有吉の壁を見始めたきっかけは、「シソンヌのコンビニバイト店員ネタ」でした。
登場した瞬間から妙に空気が重く、「あ、これはただのネタじゃない」と思ったのを覚えています。
ツッコミが入る前から、物語が始まっている感じ。その“異常な日常”にどっぷり浸かってしまいました。
「設定だけで笑える」って、実はすごいことだなと改めて感じた瞬間です。
—
#### 【まとめ】“世界観構築型”コントは令和の主流になる
『有吉の壁』の魅力は、ただ笑えるだけではなく、
「短い時間で、いかに強い世界観を届けられるか」に挑戦しているところにあります。
今の視聴者は、“くだらなさ”の中にも“筋の通った笑い”や“物語”を求めています。
それを満たしてくれる芸人たちが、この番組には揃っているのです。
令和のお笑いは「キャラ」「世界観」「物語性」が鍵。
その最前線が、有吉の壁だと言っても過言ではありません。